動悸・息切れ
 胸が苦しく感じたり、締めつけられるような違和感がある場合、それは動悸や息切れのサインかもしれません。こうした症状の背景には、様々な疾患が関係している可能性があり、心臓が原因なのか、肺など別の臓器が関係しているのかを判断するのは簡単ではありません。
胸が苦しく感じたり、締めつけられるような違和感がある場合、それは動悸や息切れのサインかもしれません。こうした症状の背景には、様々な疾患が関係している可能性があり、心臓が原因なのか、肺など別の臓器が関係しているのかを判断するのは簡単ではありません。
原因には、不整脈や心不全、狭心症、心筋梗塞、肺炎、肺血栓塞栓症、気胸、呼吸不全、喘息のほか、甲状腺機能亢進症や貧血、不安、お薬の副作用、過換気症候群などが考えられます。
動悸や息切れの原因は、心血管・呼吸器・内分泌系など多岐にわたるため、症状に気づいた時点で早めに当院までご相談ください。
動悸・息切れの原因
動悸や息切れがあるときは、心臓や肺、もしくはその両方に何らかの異常が起きていることがあります。これらの臓器に疾患があると、体が必要とする酸素を十分に供給できなくなり、特に運動時などに心肺の働きが過剰に活発になることで、動悸や息切れといった症状が現れます。
健康な方でも激しい運動をすれば呼吸が苦しくなることはありますが、軽い動作でも息切れを感じるようであれば、何かしらの病気が隠れている可能性があるため、医療機関を受診しましょう。
また、心臓や肺に異常がなくても、甲状腺機能亢進症によって代謝が活発になり、結果として酸素不足が起きて動悸や息切れに繋がるケースもあります。
さらに、貧血によって血液の酸素運搬能力が低下した場合や、精神的なストレス・不安・パニック障害などの心因性の原因でも、心拍数や呼吸数が急に増加し、同様の症状を引き起こすことがあります。
動悸・息切れから疑われる疾患
脈が速い(不整脈)
不整脈とは、心臓の拍動が正常ではなくなった状態です。健康な心臓は1分間に60〜70回ほどの一定のリズムで動いていますが、不整脈では、脈が急に速くなったり(120回以上)、反対に極端に遅くなったり(40回以下)します。不整脈が生じると、動悸や息苦しさ、ふらつき、失神といった症状が起こります。
脈が速くなるタイプの不整脈の1つに心房細動があります。通常は、右心房にある洞結節が発する電気信号によって、1分間に60〜100回程度の整ったリズムで心臓が拍動します。しかし、心房細動では心房内に複数の異常な電気信号が発生し、心房が1分間に400〜600回というスピードで細かく震えるようになります。これにより、動悸やめまいなどが起こります。
また、心房細動は放置すると、脳梗塞の発症リスクが約5倍、心不全のリスクも約4倍に高まるとされており、早期の診断と治療が大切です。
疑われる疾患
発作性頻脈などの不整脈
脈が遅い・飛ぶ
脈拍が通常よりも遅い場合、洞不全症候群や房室ブロックなど、徐脈性不整脈が関係している可能性があります。これらの不整脈が起こると、心臓が全身に十分な血液を送れなくなり、息切れや疲れやすさ、さらには脳への血流不足によって意識が遠のくこともあります。重症化すると、突然死のリスクもあるため、必要に応じてペースメーカーの植え込みが検討されることもあります。
一方で、脈が「飛ぶ」と感じる場合には、期外収縮が関係していることがあります。これは、心臓の通常とは異なる場所から電気信号が出ることで、拍動のタイミングが乱れる状態です。
電気の異常が心房で起こる場合は上室性期外収縮、心室で発生する場合は心室性期外収縮と呼ばれ、いずれも比較的よく見られる不整脈です。健康診断などで指摘されることも多く、30代以降では多くの方に認められます。
自覚症状がないこともあれば、強く胸に違和感を覚えるなど、症状の程度には個人差があります。
疑われる疾患
洞不全症候群や完全房室ブロック、期外収縮などの不整脈
動悸
動悸とは、普段は意識しない心臓の鼓動を強く感じるようになる状態で、不安や緊張、興奮などの影響で一時的に強まることがあります。病気が原因とは限りませんが、動悸が長引いたり、頻繁に繰り返されたりする場合は、循環器の専門医に相談しましょう。
動悸の原因は多岐にわたりますが、重篤な心疾患が隠れている場合もあります。原因として多いのが不整脈で、特に高齢者に多く見られますが、若い年代でも起こることがあります。
なかでも心房細動は代表的な不整脈の1つで、年齢とともに増加傾向にあり、男性に起こることが多いです。
疑われる疾患
心房細動などの不整脈、狭心症、貧血、甲状腺疾患など
動悸・息切れの検査
動悸や息切れが起きている場合、その背景には心臓や肺の病気、あるいは貧血などの血液の異常が関係していることがあります。まずは問診で症状の経過や生活習慣などを伺い、そのうえで必要に応じて各種検査を行います。以下が主な検査です。
心電図検査
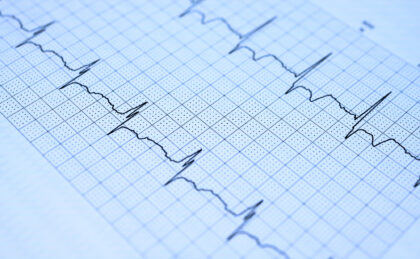 心臓の電気的な活動を一定時間記録し、脈のリズムや異常がないかを確認します。
心臓の電気的な活動を一定時間記録し、脈のリズムや異常がないかを確認します。
血液検査
血液の成分を調べることで、甲状腺機能、貧血の有無、電解質のバランスなどを確認します。
ホルター心電図
小型の心電計を装着し、日常生活の中で心拍の変化を継続的に記録する検査です。不整脈は一時的にしか現れないことが多いため、短時間の検査では見逃されることがあります。
ホルター心電図を行うことで、不整脈が出たタイミングを逃さずに記録できる可能性が高まります。昨今は、スマートウォッチを併用するケースもあります。
心臓超音波検査
 超音波を使って、心臓の構造や動き、弁の開閉の状態などを詳しく観察します。
超音波を使って、心臓の構造や動き、弁の開閉の状態などを詳しく観察します。
動悸・息切れの治し方
 息切れの原因が心臓にある場合は、心不全や弁膜症、不整脈、冠動脈疾患など、原因に応じた適切な治療が必要です。治療法には、生活習慣の改善、薬物療法、外科手術などがあり、患者様の状態に合わせて選択されます。
息切れの原因が心臓にある場合は、心不全や弁膜症、不整脈、冠動脈疾患など、原因に応じた適切な治療が必要です。治療法には、生活習慣の改善、薬物療法、外科手術などがあり、患者様の状態に合わせて選択されます。
なかでも多くみられるのが心不全です。心不全とは、全身に必要な酸素や栄養を届けるための血液を、心臓が十分に送り出せなくなっている状態です。心臓の機能が低下すると、体内に水分が溜まりやすくなり、特に肺に水分が溜まることで息苦しく感じます。
そのため、塩分や水分の摂取を制限したり、心臓の働きを助けるお薬を使用するなどの対応が行われます。なお、手術が必要と判断される場合は、連携する高度医療機関をご案内します。
生活習慣の見直し
塩分や水分の摂りすぎを控えることが重要です。よく「健康のために1日2ℓの水を飲むと良い」と言われますが、心機能が低下している方にとっては、体内に余分な水分が溜まりやすくなり、症状を悪化させる原因となるため注意しましょう
薬物療法
心臓の働きをサポートして脈のリズムを整えるお薬や、体内に溜まった余分な水分を排出する利尿薬などを組み合わせながら、患者様の状態に合わせた最適な治療を行います。
動悸・息切れの対処法
動悸が起きたときは、ゆっくりと息を吐くことを意識しながら、数回深呼吸を行ってみましょう。お腹の動きを意識しながら呼吸することで、副交感神経が優位になり、気持ちが落ち着きやすくなります。
気分が少し和らいだら、ハンカチなどにアロマオイルを数滴たらし、香りを吸い込むように深呼吸するのも、自律神経のバランスを整えるのに効果的です。
また、動悸の多くは自律神経の乱れと関係しているため、生活習慣の見直しも重要です。
日中はしっかりと太陽の光を浴びること、適度な運動を取り入れること、そしてカフェインやアルコール、喫煙を控えるなど、毎日のリズムを整えることで症状の改善が期待できます。
ただし、動悸や息切れは重大な病気の兆候の場合があります。特に突然現れる場合や長く続くような場合は、自己判断せず早めに医療機関を受診し、原因を明らかにすることが大切です。



